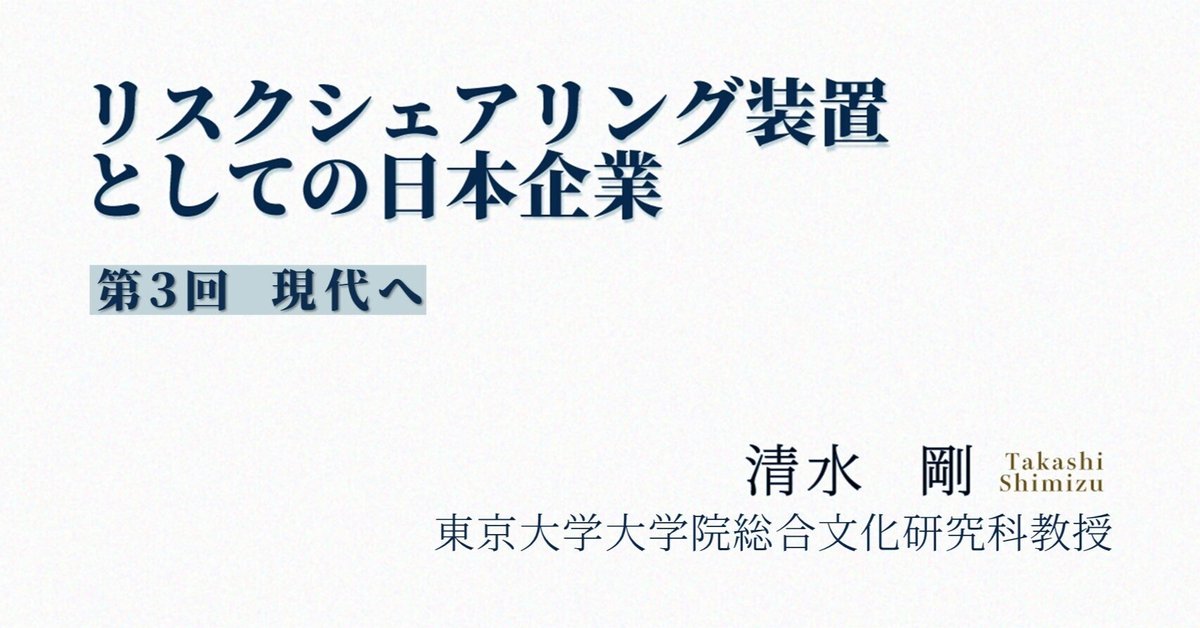
リスクシェアリング装置としての日本企業(第3回) 現代へ
1.戦後における企業と消費者、株主との関係
前回述べたように、戦後においては企業が一方的に将来の不確実性に対応する手段を提供するというよりも、企業と労働者はそれぞれの将来の不確実性を共有するという形で対応してきたと考えられる。しかし、それでは他のステイクホルダーとの関係においてはどうだったのだろうか。言い換えれば、同じようなやり方は消費者あるいは株主と企業との関係においてみられたのであろうか。
(1)企業と消費者とのリスクシェア
まず、消費者との関係においてリスクシェアリングというのは、企業が消費者との間でネットワークを構築し、あるいは信頼を形成することで安心してものを買える仕組みが形成される一方で、企業側のリスクや不確実性、典型的には需要変動を消費者側がある程度引き受けるような仕組み、ということになる。企業間取引の例でいえば、例えば部品の納入において、顧客の側も業者を切り替えたり、値段を市場変動に応じて上げ下げするのではなく、予定した価格で少なくとも一定期間納入するというような契約、すなわちサプライヤー関係の中でみられた契約(浅沼・菊谷, 1997)が1つの典型といえるかもしれない。ここまで典型的なものでなくても、いわゆる得意先との間で関係を構築し、得意先が値段を切り下げたりしない代わりに得意先の要望に応える、というのは決して珍しい取引形態ではなかったように思われる。
それでは、消費者の場合にはどうなのだろうか。この点については生活協同組合(以下「生協」)が1つの例となるだろう。生協そのものはあくまで組合であり、企業ではないが、事業体という意味では将来の事業に関する不確実性やリスクに直面する。これに対して、各地の生協は例えば共同購入や予約による計画的な購入という形で食料などの必要なものを安定的かつ安価に組合員に供給する一方で、生協自体が見込みで仕入れてそれを販売するのではなく、このような計画的購入や組合員の共同購入という形にすることで、売れ残りなどのリスクを組合員と共有することができる。実際、戦後の食糧危機の時期には共同購入によって食料を確保するための多くの生協が組織されたが、このような共同購入のみならず、予約による計画的な購入を取り入れることでリスクシェアリングが進んできた。この2つはしばしば予約共同購入という形で取り入れられ、現代でも利用されている(日生協創立50周年記念歴史編纂委員会, 2002, 上84-85頁, 126-127頁,304-306頁)。
あるいは、酒販店、いわゆる酒屋と消費者の関係を考えると良いかもしれない。戦後しばらくの間、酒販店の商圏は狭く、地域の酒屋と消費者とは長期的な付き合いがあり、しばしば御用聞きや宅配のような形で取引をしていた(注1)。酒屋の側からみれば、ある地域の消費者が安定的に購入してくれることで、事業のリスクを下げることができたわけである。労働者のようにリスクシェアリングの仕組みが制度や慣習になったというわけではないものの、不確実性やリスクの共有というやり方は消費者や顧客との関係でもある程度機能してきたように思われる。
(注1)例えば今西 (1976) 。なお、「サザエさん」のテレビアニメ版に登場する御用聞き、サブちゃんの勤め先が三河屋という酒屋であることはこのような状況を典型的に示している。朝日新聞社be編集部 (2005, 186-189頁)参照。
(2)企業と株主とのリスクシェア
株主についていえば、株主が企業(経営者)の方針に賛同し、短期的な配当の最大化を求めるのではなくて、企業の長期的な成長を考え、一方で経営者は企業が成長すれば高い配当を払うというのが『感染症と経営』(清水, 2021a)で述べた株主と企業の関係である。ここで、リスクシェアリングという場合には、株主もまた、例えば株価が下がってもすぐに株式を売却せず、経営者を支持し続けるというようなことになろう。
もともと、株主は企業の不確実性やリスクを一部負担しているが、株主には業績が下がるリスクがあれば株式を売る、あるいは経営者を交代させるというオプションがある。そのようなオプションをすぐには行使せず、業績が下がるリスクを負担してでも株式を保有し、(限度はあるものの)経営者を支持するというのが上で述べたリスクシェアリングのやり方ということになる。そしてこれは、実際に安定株主あるいは株主持合いという実務慣行の中でしばしばみられたものである。
安定株主についていえば、例えば金融機関や取引先、従業員などが株式を保有し、株価が下がってもすぐには売却せず、またすぐに取締役の解任を求めることもない。このような形でリスクを共有することで、株価の下落や解任を恐れずに経営者が経営を行うことを可能にする(e.g., Abegglen and Stalk, 1985, Aoki and Patrick, 1994)。さらに、一部の大企業でみられた持合い関係はこのようにリスクや不確実性をお互いに負担し合うものということになる(注2)。
(注2)例えば宮島・原村・江南(2003)は、持合い株主を含む安定株主の典型的な例として金融機関と事業法人間の株式保有に焦点を当てて統計分析を行い、安定株主化が進展する1965-74年において金融機関が安定株主化の進展において経営の効率化の改善を伴う安定株主化とそうでない安定株主化を識別していたことなどを示しているが、これは金融機関がリスクがリターンに見合わない場合には安定株主とならないことを意味しており、合理的なリスク共有行動としての安定株主という本論の見方と整合的である。
(3)「依存」関係への変容
このように考えてくると、上で述べた仕組み、すなわち企業とステイクホルダーがお互いの不確実性やリスクを共有することで、長期・安定的な関係を維持しようとすることは消費者や株主においても一定程度みられたといえるだろう。また、そのような関係からの退出が難しくなると、特定の企業への依存が生じる、という現象もとりわけ株主においてみられたように思われる。持合いの場合は相互的なので必ずしもそうではないが、安定株主の場合にはすぐに株式を売却するということが難しいため、企業が株主に対してパワーを持つということが生じうる。この結果、例えば経営者の解任が難しくなるというようなことが起こりうるわけである。消費者の場合には一般的には退出が容易であるためにこのような問題は起こりにくいが、例えば酒販店との関係でいえば、ある地域に酒販店が1つしかないというような状況であればその酒販店が消費者に対してパワーを持つことが起こりうる。
2.そして現代
(1)日本的リスクシェアリング経営は時代遅れか?
さて、これまで日本において利用されてきた、このようなリスクシェアリングの仕組みは現代においてどこまで利用可能なものなのだろうか。現代ではいわゆる日本的経営は時代遅れということになっており、例えば労働者との関係についてもジョブ型雇用の導入に向けて動きつつある。上で述べたように、こうした仕組みは戦後直後の状況への対応から始まっていることを考えれば、「時代遅れ」という批判も全く間違ったものとは思わないが、しかしその中で何が現代においても利用でき、何が利用できないのかをやはりきちんと切り分けるべきだろう。
このように考えたときに、このような仕組みそのものが利用できるかどうか、という点と、企業への依存が引き起こす問題にどう対応するかというのは別の問題であることに気がつく。とりわけ、今後感染症の影響で、あるいはその他の要因により将来のリスクあるいは不確実性が拡大するのだとすれば(なお清水, 2021b参照)、そのような不確実性やリスクに対応する方法はやはり考えておくべきだろう。
そして、『感染症と経営』(清水, 2021a)でも述べたように、やはり上のような仕組みそのものは現代においてもなお利用可能な、言い換えれば意味のあるものではないかと思われる。個人が直面する不確実性やリスクに対して、すべて政府が対応するというのは財政的な負担を考えてもおそらく現実的ではない。企業をいわば「利用」することで将来の不確実性やリスクに対応できるのであれば、それは十分に考慮に値する。また、その際に企業の不確実性やリスクをステイクホルダーが共有することで相互に長期・安定的な関係を維持できる可能性が高まるのであれば、企業が直面する不確実性やリスクをステイクホルダーが負担することもありうるだろう。
(2)リスクの過剰な転嫁?
実際に、企業とステイクホルダーがリスクや不確実性を共有する仕組みはしばしばみられる。例えば、このシリーズの前回の論考(「『風立ちぬ』、樋口一葉そしてUber運転手」)で述べたように、Uberの運転手やUber Eatsの配達員のような雇用関係にない人々(いわゆるギグワーカー)を雇用関係に取り込む動きはすでに各国でみられる。これは個人が直面する不確実性やリスクが高すぎる場合に、企業との雇用関係を設定することによりその一部を企業に負担させようとするものである。ただし、一方でこれらのギグワーカーはそもそも企業が雇用するという形をとらないことによって企業が直面する不確実性を労働者自身に負担させようとするものでもあり、この意味で雇用されている労働者とは異なる形でリスクや不確実性が共有されている。
消費者についていえば、D2C(Direct to Consumer)というのはまさに消費者との直接的な関係を構築することで、消費者が安心してものを買うことができるようにするものである(注3)。企業にとっても、D2Cによって関係を構築し、消費者を囲い込むことで需要変動のリスクをある程度避けることができる。
また、いわゆるサブスクは一定料金を定期的に払うことで企業のリスクや不確実性を低減させる(必要がなくてもお金を払うことになる可能性があるという意味で、このリスクは消費者が負担している)一方で、消費者は一定の品質の財またはサービスを安定的に手に入れることができる。
また、安定株主自体は現在では少なくなったものの、株価が下がったら株式をすぐに売却するというのではなく、経営者と対話しながら改善の方向性を探る(とりわけ、実際の経営に関与するハンズオンの形で)株主、例えば一部の機関投資家やベンチャー企業に対する一部の投資ファンド等はまさにリスクや不確実性を共有する存在といえるだろう。
問題は、どの程度企業のリスクを個人が負担するのかである。というのは、上で述べたように企業に対する依存が発生しているならば、企業はその依存関係に基づいてステイクホルダーに対するパワーを持つようになるために、そのパワーを行使して、企業が直面するリスクや不確実性をできる限りステイクホルダーに転嫁しようとするだろう。例えば、売上が下がったときには賃金を大幅にカットする、あるいは長時間のサービス残業をさせるなどが考えられる。企業への依存は労働者において一番典型的にみられるが、先に述べたように安定株主のような場合でも起こりうる。この場合は株主への利益還元策を行うことなく、またそれを投資に回すでもなく資金をため込んでいるような例が考えられる。
こうなってしまうと、企業とステイクホルダーがwin-winになる関係から、企業が一方的に利益を得るのに対しステイクホルダーは必ずしも得をしない(将来に関する不確実性は企業によって吸収されても、残業や賃金カットのような形で企業が直面するリスクや不確実性を負担することでステイクホルダーからみたネットの利益がマイナスとなる)関係へと変容している。あるいは、ある特定のステイクホルダーが得をし、別の種類のステイクホルダーが損をするということも起こるかもしれない。しかし、このような企業をステイクホルダーが支持することはなく、長期的にはその企業のステイクホルダーという立場からの退出を選択するだろう(March and Simon, 1958, ch.4)。すなわち、ステイクホルダーにとって利益をもたらさないような企業は長期的には持続可能ではない。
(注3)この点は川戸崇志氏の指摘による(川戸, 2021も参照)。記して感謝したい。
(3)適切なパワーバランス
このように考えると、今後、感染症等により不確実性が増大する世界で、上のような仕組みが利用可能であるかどうかは、企業とステイクホルダーとの間でパワーバランスをとることができるかどうかに依存している。もし適切なパワーバランスがとられ、企業が自らが直面する不確実性やリスクをステイクホルダーに過剰に転嫁するということがなければ、上のような仕組みは不確実性に対応するための1つのやり方として今後も利用されうるだろう。しかし、企業のほうにパワーがあるのであれば、ステイクホルダーが企業に(古い言葉だが)搾取されるような状況になりかねない。
いわゆるブラック企業の問題点の1つは、なかなか辞められない労働者が企業に最大限搾取されることであると思われる。こう考えれば、ブラック企業にならないためにも、ステイクホルダーとの間の適切なパワーバランスを維持すること、言い換えれば企業への依存を減らし、あるいは企業に対抗するパワーを与えることが必要になる。ブラック企業を例にとっても明らかなように、とりわけこのようなパワーバランスが問題になるのは労働者との関係であろう。労働者が企業に対抗するために労働組合を利用できるようになる、あるいは転職できる程度の能力を保有するというのはその方法の例である(清水, 2021a, 第6章)。
企業のステイクホルダーに対するパワーが低下することは企業としては望ましくないように見えるかもしれないが、必ずしもそうではない。例えば、企業の労働者に対するパワーが減少すれば、企業の「望ましい労働者像」を押し付けることができなくなり、労働者の自律性や多様性が高まるだろう。現代社会においては、このような労働者の自律性や多様性はイノベーションを促進するという意味でも望ましいものであり、また社会的にも望ましいとされるものである。すなわち、かつてのようにステイクホルダーが企業の都合に合わせるのではなく、企業が様々に異なる事情と背景を持つ人々をいかに受け止めるかということを考えることが必要になっていると思われる(この点については清水, 2021b)。いささか楽観的な見通しを付け加えれば、このような自律性が高まることで一定の人々が移動できるようになり、労働市場の流動性が高まることで、再就職者の就職機会も拡大していく可能性がある。
リスクや不確実性を共有することで、企業とステイクホルダーがともに将来を生きやすくなる。ただし、そのためには、企業とステイクホルダーとがいわば対等の立場にたち、お互いにとって有益なように関係を結ぶことができることが前提となる。これまでの日本企業では歴史的な経緯もあり、企業側が有利な立場となり、不確実性やリスクをしばしばステイクホルダーに過剰に転嫁してきたのではないだろうか。経営を変える必要があると日本企業が思うのであれば、まずステイクホルダーとの間に対等な関係を作るところから始めてはどうだろうか。
参考文献
浅沼萬里・菊谷達弥 (1997) 『日本の企業組織 革新的適応のメカニズム:長期取引関係の構造と機能』東洋経済新報社.
朝日新聞be編集部編 (2005) 『サザエさんをさがして』朝日新聞社.
今西武 (1976) 「厚い需要の壁に苦悩する酒販業界」『日本醸造協会雑誌』71(7), 484-487.
川戸崇志 (2021) 「読書レビュー『感染症と経営; 戦前日本企業は「死の影」といかに向き合ったか』」
清水剛 (2021a) 『感染症と経営:戦前日本企業は「死の影」といかに向き合ったか』中央経済社.
清水剛 (2021b) 「『不確実性の時代』に生き残る企業」『Voice』525, 76-83.
日生協創立50周年記念歴史編纂委員会 (2002) 『現代日本生協運動史』日本生活協同組合連合会.
宮島英昭・原村健二・江南喜成 (2003) 「戦後日本企業の株式所有構造:安定株主の形成と解消」『フィナンシャル・レビュー』68, 203-236.
Abegglen, James C., and George Stalk, Jr (1985) Kaisha: The Japanese Corporation. New York: Basic Books. (植山周一郎訳『カイシャ:次代を創るダイナミズム』講談社, 1986年)
Aoki, Masahiko, and Hugh Patrick (eds.) (1994) The Japanese Main Bank System: Its Relevance for Developing and Transforming Economies. Oxford: Oxford University Press.(東銀リサーチインターナショナル訳『日本のメインバンク・システム』東洋経済新報社, 1996年)
March, James G., and Herbert A. Simon (1993) Organizations, 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell (高橋伸夫訳『オーガニゼーションズ(第2版):現代組織論の原典』ダイヤモンド社, 2014年)
著者略歴
清水 剛(しみず・たかし)
東京大学大学院総合文化研究科教授
1974年生まれ。1996年東京大学経済学部卒業、2000年同大学大学院経済学研究科修了、博士(経済学)。東京大学大学院総合文化研究科専任講師、同助教授、同准教授を経て現職。この間、ソウル大学、ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで客員教授、イェール大学、カリフォルニア大学バークレー校で客員研究員を務める。専門は経営学、経営史学、法と経済学で、とりわけ企業システムおよび企業経営と法制度の相互作用に関する研究を行っている。
Twitter:https://twitter.com/TakashiShimiz17
researchmap:https://researchmap.jp/takashipandashimizu
【清水先生・連載のご紹介】
感染症と「死」、そして企業経営
第1回 戦前の日本社会から「コロナ後」を考える
第2回 三越・主婦之友・生協はなぜ誕生したか
第3回 戦前日本企業は短期志向をどのように克服したか
第4回 「風立ちぬ」、樋口一葉、そしてUber運転手ー『感染症と経営:戦前日本企業は「死の影」といかに向き合ったか』へのイントロダクション

